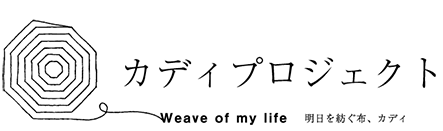カディプロジェクトは、インド・ビハール州ブッダガヤで雇用を作るために活動してきた合同会社ニマイニタイのブランドを通して、任意活動として本格的に走り出したプロジェクトです。
プロジェクトメンバー紹介

廣中桃子
合同会社nimai-nitai 代表
NIMAI NITAI/デザイナー
カディプロジェクト発起人
「援助では本当の意味で自立はできない。汗水流して、力強く生き抜いて欲しい。」
ブッダガヤを初めて訪ねたのが2007年。11年の歳月が経たった今でも、何度訪ねても、いくら長く滞在しても、この土地での私は外国人であることに変わりはなかった。
それは、いくら現地のためにやっていたとしても、自分のエゴに過ぎないという事を自覚する、ということの繰り返しでした。
それでも、何ができるだろうかと、その意味を考え続け、フェアトレードと呼ばれるビジネスを通した関係が、この村と繋がり続けれるひとつの答えでした。
それも、数年が経ち、疑問が生まれ、フェアトレードと呼ばれる貿易ビジネスには、根気とセンス、そして経験が必要で、フェアトレードで携われる人はごく限られてしまう。
もっと、土着的に、彼らの生活スタイルを壊さず働ける、継続的な仕事はないだろうか。
その答えがカディであることに確信するまで、そう時間はかかりませんでした。
糸を紡ぐことは、平和を紡ぐこと、そのものです。
このプロジェクトのスタートは、自立の道へのスタートライン。
数年先、数十年後に、プロジェクトの答えが出るときまで、この土地に関わり続けること。
女性たちが紡いだ糸が、いつかニマイニタイの洋服の糸になるまで、そう遠くはないと思っています。
援助が必要でなくなるその時まで、それがこのプロジェクトの最終目標地だと思っています。
応援サポーター

倉石寛先生
立命館大学稲盛経営哲学研究センター 副センター長
 立命館大学OIC総合研究機構 稲盛経営哲学研究センター 副センター長。2011~2015立命館大学教育開発推進機構教授、立命館附属校教育研究・研修センター長。1971~2014年度にかけて私立灘中学・高校で日本史の教鞭をとる。教頭時代には「土曜講座」を開講、卒業生を中心に、ソーシャルな活動をする専門家・実務経験者を招き、灘高生に偏差値を超えたキャリアについて考えさせる。歴史教育者協議会のメンバーでもある。
立命館大学OIC総合研究機構 稲盛経営哲学研究センター 副センター長。2011~2015立命館大学教育開発推進機構教授、立命館附属校教育研究・研修センター長。1971~2014年度にかけて私立灘中学・高校で日本史の教鞭をとる。教頭時代には「土曜講座」を開講、卒業生を中心に、ソーシャルな活動をする専門家・実務経験者を招き、灘高生に偏差値を超えたキャリアについて考えさせる。歴史教育者協議会のメンバーでもある。
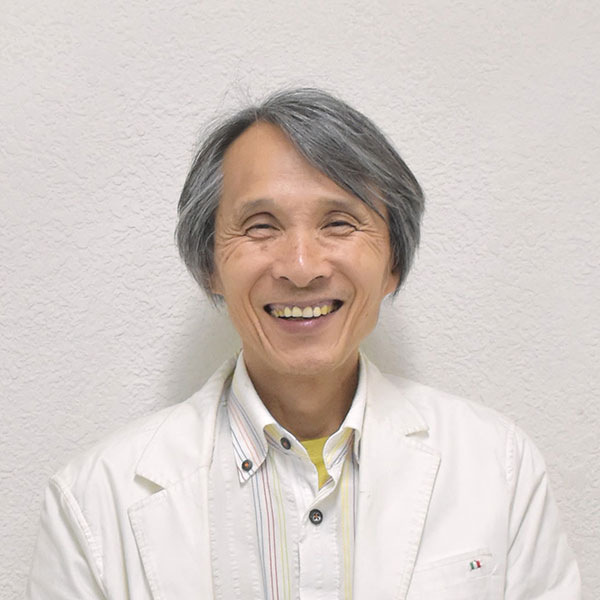
金井文宏先生
立命館大学稲盛経営哲学研究センター研究員 客員教授
 高等学校社会科教員(兵庫県)、(株)シティーコード研究所(都市計画事務所)、(株)西洋環境開発を経て、現在、株式会社都市文化研究所 代表取締役(1992年~)
高等学校社会科教員(兵庫県)、(株)シティーコード研究所(都市計画事務所)、(株)西洋環境開発を経て、現在、株式会社都市文化研究所 代表取締役(1992年~)
甲南女子大学人間科学部(教育学)非常勤講師(2003年~)
協賛
 学校法人安城学園 様
学校法人安城学園 様

寺部 曉
学校法人安城学園 理事長
学校法人安城学園は、官尊民卑・男尊女卑の風潮が極めて強かった明治の末期に女性の社会的(=経済的・政治的・文化的)自立を実現するために裁縫女学校を設立しました。「誰でも無限の可能性を持っている」という創立者の信念が原点になっています。
NIMAI-NITAI の社会貢献活動に今回協賛させていただいたのは、「裁縫技術の習得を通してブッダガヤの女性の社会的自立を支援したい」というカディプロジェクトの基本コンセプトが創立者の信念と一致していて共感できたからです。このプロジェクトがブッダガヤの女性の潜在能力の開発に役立つことを心から念願しています。
学園では、新しい教育システム「学びの泉」の開発に取り組んでいます。皆様のプロジェクトに対する真摯な取り組みは学園の学生・生徒にとって「生きた教材」となりますので、今後ともWin-Win 関係に基づいた相互連携ができればと考えています。
最後に、ブッダガヤの人々が社会的に自立され、「生きる意志と生きる力と生きる歓びに満ち溢れた人生を送ることができますよう!」心からご祈念申し上げます。
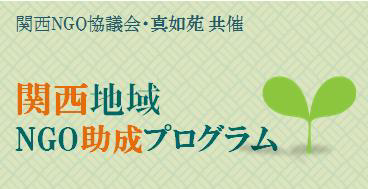
関西地域NGO助成プログラム(関西NGO協議会・眞如苑催)
インド現地体制(インド・協力メンバー)
- KARVEEN SINGH
- NIMAI-NITAI現地パートナー代表
- カディ組合ビハール州本部
- カディ組合ガヤ本部代表:Sunil Kumar
カディ組合ガヤ本部福代表:Kapil Kumar
カディ組合ガヤ本部ブッダガヤカディ組合シニア代表 - Indardav Choudhary
- ハティヤール村村長
- NIKESH KUMAR
- ハティヤール村学校(AOZORA Welfare Trust)校長
- PAPU KUMAR
- ブッダガヤ建設資材会社社長
事務局概要
-
事務局
カディプロジェクト事務局
(合同会社 NIMAI-NITAI) -
住所
滋賀県近江八幡市出町59
-
代表
廣中 桃子